こんにちは。高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」です。
口を開けたり閉じたりするたびに顎が痛んだり、カクカクと音が鳴ったりすることはありませんか。顎関節症は誰にでも起こりうる身近な症状ですが、放置すると食事や会話が困難になるなど、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
この記事では、顎関節症の原因や治療法、予防法などについて解説します。顎の痛みや違和感に悩んでいる方や、予防法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
顎関節症とはどんな病気?
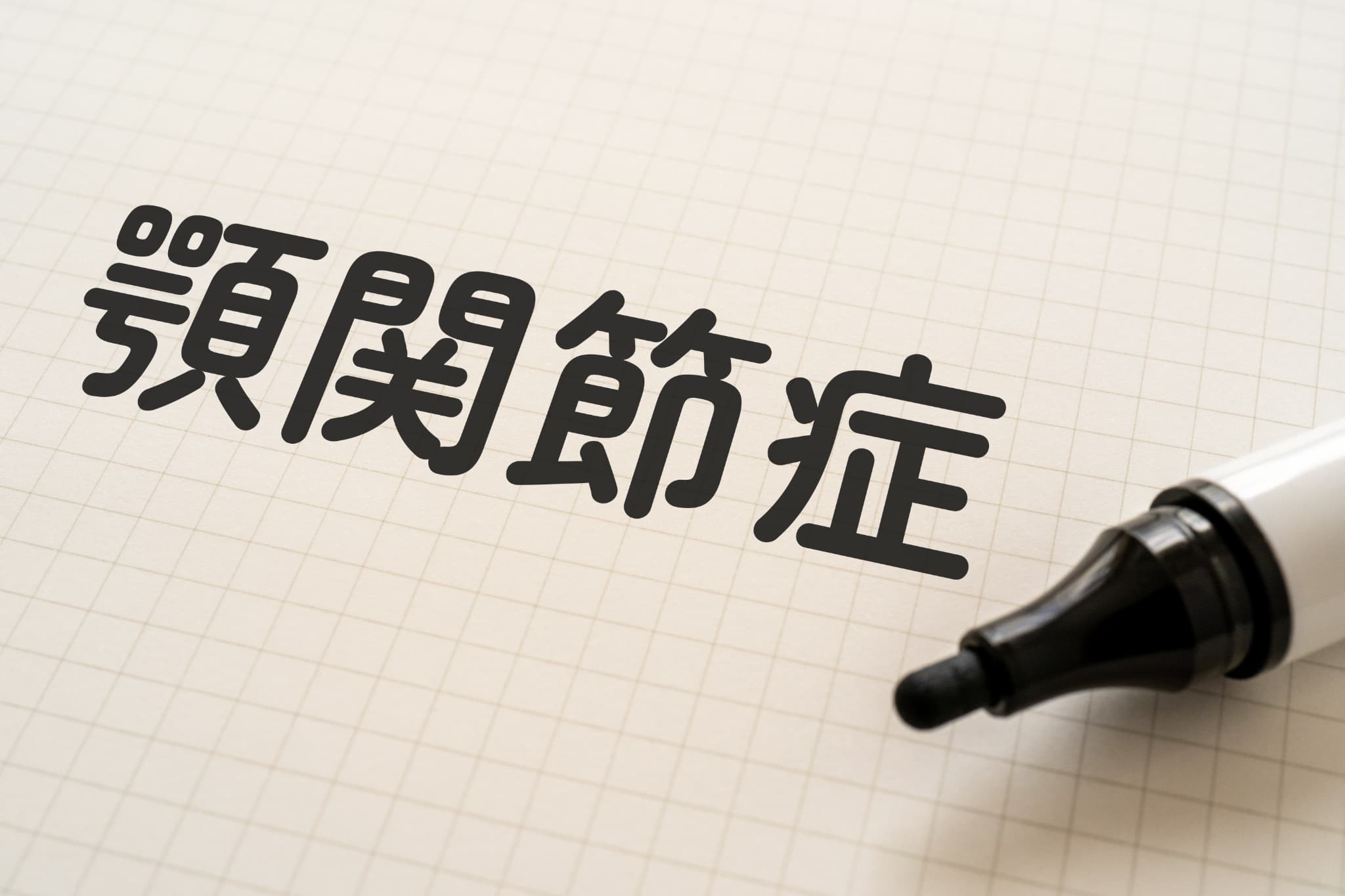
顎関節症は、顎の関節やその周囲の筋肉に不調が生じる病気です。顎関節症になると、次のような症状が現れます。
- 口を開け閉めすると顎が痛い
- 顎関節部分からカクカク、ジャリジャリといった音が聞こえる
- 口が大きく開きにくい
- 顎がスムーズに動かない
これらの症状は、顎関節そのものや周囲の筋肉、靭帯、さらには噛み合わせの異常など、複数の要因が複雑に関与して発生すると考えられています。
顎関節症は特定の年齢や性別に限らず幅広い年代でみられ、症状の程度や現れ方には個人差があります。放置すると、日常生活に支障をきたすこともあるため、気になる症状がある場合は早めに専門医へ相談することが大切です。
顎関節症の主な原因

顎関節症を発症する原因は一つではなく、さまざまな要因が複雑に関係していると考えられています。
噛み合わせの異常
噛み合わせが悪いと、上下の歯がうまく接触せず、顎の関節や周囲の筋肉に偏った力がかかりやすくなります。このような状態が続くと、関節や組織にストレスが蓄積し、症状が現れることがあるのです。
ストレスや精神的な要因
精神的な緊張やストレスが強いと、無意識に顎の筋肉が緊張したり、食いしばる癖が出やすくなったりします。これが長期間続くことで、顎関節症の症状が現れる場合があるのです。
歯ぎしり・食いしばりの習慣
歯ぎしりや食いしばりは、無意識のうちに歯や顎に強い力がかかる習慣です。
特に睡眠中や集中しているときなど、自覚のないまま続いていることが多く、顎の関節や周囲の筋肉に大きな負担を与えます。これが慢性的に続くと、痛みや開閉障害などの症状が出ることがあります。
姿勢や生活習慣の乱れ
長時間のスマートフォンの使用やパソコン作業などで姿勢が悪くなると、顎や首周りの筋肉に負担がかかります。また、頬杖やうつぶせ寝などの習慣も顎関節症のリスクを高めることが知られています。
外傷や怪我によるもの
転倒や事故などで顎や顔面に強い衝撃を受けると、顎の関節や周囲の組織が損傷し、顎関節症を引き起こす可能性があります。
外傷後に違和感や痛みが続く場合は、そのまま放置せず、早めに歯科医院を受診しましょう。
その他のリスク要因
遺伝的な要素や、ホルモンバランスの変化、関節リウマチなどの全身的な病気も、顎関節症の発症に関わる場合があります。また、これらの要因が重なることで、症状が現れることもあります。
顎関節症の症状と日常生活への影響

先述したように、顎関節症の代表的な症状には、顎の痛みや開閉時の音、口の開けにくさが挙げられます。これらの不調は、食事や会話、歯磨きといった日常的な動作にも支障をきたすことがあり、生活の質に影響を与えることがあります。
また、顎だけでなく、頭痛や肩こり、耳の違和感などを訴える方も少なくありません。症状の現れ方や強さには個人差があり、軽い違和感で済む場合もあれば、強い痛みや不快感が続くケースもあります。
「少し痛むけれど我慢できるから」と放置していると、症状が徐々に悪化し、慢性的な痛みや顎の動きに制限が出てくる可能性があります。負担がかかり続けることで、関節の変形や顎の機能障害につながることも否定できません。
こうした状態になると、食事がしづらくなったり、発音がうまくできなくなったりするなど、コミュニケーションにも大きな影響が出ることがあります。違和感や痛みが続く場合は、早めに歯科医院などで相談し、適切な治療を受けることが大切です。
顎関節症のセルフチェックと予防方法

顎関節症のセルフチェック方法や、日常生活での予防策について解説します。
自分でできる症状チェック
顎関節症の症状は、ご自身でも確認できます。
口を大きく開けたり閉じたりしたときに痛みや違和感があるか、カクカクと音が鳴るか、また口が指3本分以上開くかどうかをチェックしてみましょう。これらの症状が続く場合は、早めに専門医に相談してください。
日常生活で意識したい予防策
顎関節症を予防するためには、日常の習慣を見直すことが重要です。
無意識に歯を食いしばる癖や、片側だけで物を噛む習慣、頬杖をつく姿勢などは顎関節に負担をかけやすい習慣です。また、ストレスが筋肉の緊張を高めることもあるため、リラックスできる時間を意識的に作ることも予防につながります。
顎関節症の治療法と医療機関の選び方

顎関節症の主な治療法と、症状が出た場合にどの診療科を受診すべきかを解説します。
主な治療法
顎関節症の症状の程度や原因は人によって異なるため、治療法も一人ひとり異なります。治療には以下のようないくつかの方法があります。
- スプリント療法(マウスピース):歯ぎしりや食いしばりによる負担を軽減
- 理学療法:顎周囲の筋肉の緊張をほぐすためのマッサージや運動療法
- 薬物療法:痛みや炎症を抑えるための筋弛緩薬・鎮痛薬の服用など
- 生活習慣の改善:姿勢の見直し、ストレス管理、噛み癖の修正など
- 外科的治療:重症例では関節鏡手術などが検討されることもある
治療にかかる費用や期間の目安
顎関節症の治療にかかる費用や期間は、症状の程度や選択される治療法によって大きく異なります。軽度のケースでは、セルフケアや生活習慣の見直しが中心となり、通院回数も少ないことが多いです。
マウスピースを使ったスプリント療法は、保険が適用される場合もあり、費用は数千円から1万円程度が一般的です。薬による治療や理学療法を併用する場合は、別途費用がかかることがあります。
治療期間については、数週間で改善が見られる方もいれば、数ヶ月にわたって継続的なケアが必要となる場合もあります。症状の進行具合や治療の内容によって個人差があるため、初診時に歯科医師としっかり相談し、無理のない治療計画を立てることが大切です。
どの診療科を受診すべき?
顎関節症の診断や治療は、主に歯科や口腔外科で行われます。症状が顎だけでなく、頭痛や肩こり、耳の違和感など多岐にわたる場合は、耳鼻咽喉科や整形外科と連携することもあります。
まずはかかりつけの歯科医院や口腔外科を受診し、必要に応じて専門医への紹介を受けると良いでしょう。
治療後の注意点と再発予防のポイント

顎関節症の治療が終わったあとも、症状の再発を防ぎ、快適な日常生活を維持するためには、日々の生活習慣やセルフケアがとても重要です。治療後の過ごし方によって、顎への負担を減らし、症状の再発リスクを抑えることができます。
治療後に気をつけたい生活習慣
治療後は、顎に過度な負担をかけないよう心がけましょう。
硬い食べ物や、大きく口を開ける動作はできるだけ避け、食事はやわらかいものを選ぶと安心です。また、頬杖をつく、歯ぎしりや食いしばりをするなどの無意識のうちに行う癖にも注意が必要です。
ストレスも顎関節に影響を与えることがあるため、意識的にリラックスできる時間を持つことも大切です。
さらに、うつ伏せ寝や片側だけで長時間寝る姿勢は、顎に偏った力がかかる原因となるため、寝る姿勢にも気を配るようにしましょう。
再発を防ぐためのセルフケア
顎の筋肉をやさしくマッサージしたり、温めたりすることで緊張をほぐすことができます。歯科医師の指導のもとで行う顎の運動療法も、関節の動きをスムーズに保つのに役立つでしょう。
また、定期的に歯科医院で噛み合わせや顎の状態をチェックしてもらうことも、再発予防には欠かせません。もし症状が再び現れた場合は、自己判断せず、早めに専門医へ相談することが安心につながります。
まとめ

顎関節症は、顎の関節や周囲の筋肉に不調が起こることで、口が開けづらくなったり、痛みや関節音が生じたりする病気です。
原因には、ストレスや歯ぎしり、噛み合わせの乱れ、日常の癖や姿勢など、さまざまな要因が関係していると考えられています。
治療には、生活習慣の見直しやセルフケアから、歯科医院での専門的な治療まで幅広い選択肢があります。
また、治療後も再発を防ぐためのケアや、顎に負担をかけない生活を意識することが、長期的な安定につながります。自分に合った方法で、無理なく継続できるケアを取り入れながら、快適な毎日を目指していきましょう。
顎関節症の症状にお悩みの方は、高松市花ノ宮にある歯医者「中山歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、全身の健康と長寿に貢献できる長期的な視点をもった治療を行っています。専門的な歯周病治療だけでなく、予防歯科、虫歯治療、インプラント、ホワイトニングなど、さまざまな診療を行っております。
当院のホームページはこちら、ご予約・お問い合わせも受け付けております。



